
北条氏の台頭と承久の乱
源頼朝と義経との関係は、よく知られています。義経は戦の天才として知られ、平氏を壇ノ浦で滅ぼしました。屋島の合戦は、中学の国語の教科書に出てくる「扇の的」で取り上げられています。
その後、二人は不仲となり、(原因の一つに梶原景時と義経の不仲があり、景時が頼朝に義経の身勝手な行動を報告しましたが、その後、殺害されました。)義経は後白河法皇から「頼朝追討」の院宣を得ましたが、逆に頼朝に追われ諸国を家臣と逃げました。(弁慶の勧進帳が有名)そして、奥州で藤原泰衡によって平泉の「持仏堂」で妻子を差し殺し、自らも自害しました。現在の高館には義経堂があり、松尾芭蕉が「夏草や兵どもが夢の跡」と詠んだことでも有名です。こちらも国語の教科書で「奥の細道」で取り上げられています。
※実際の高館は、北上川の侵食をうけて失われたと考えられています。
※(a )〜は、定期試験・大学入試に必要な基本歴史用語です。
北条氏の台頭
将軍独裁体制が終焉し、御家人主導の政治を志向する
源頼朝の死(1199)後、2代将軍(a 源頼家 )の親裁権停止
13名の合議制:有力御家人の北条時政・梶原景時・比企能員・和田義盛ら
有力御家人による幕府の主導権争い


江ノ電の和田塚駅からすぐのところに和田塚があります。北条義時との戦い(和田合戦)で亡くなった和田一族を埋葬したと伝わっています
承久の乱
源実朝が暗殺された後に、後鳥羽上皇は全国の武士に対して「北条義時追討」の院宣を出しました。これに対して鎌倉幕府は、北条政子の有名な演説があります。御家人たちの前で、「御家人に対して行なった頼朝公のおかげで生活が豊かになった。その恩は山よりも高く、海よりも深い。もし、朝廷側の味方をするなら、自分を殺してから京都に向かいなさい」と言い放ち、御家人たちは涙を流して一致団結してわずかな期間で朝廷軍を倒したのです。
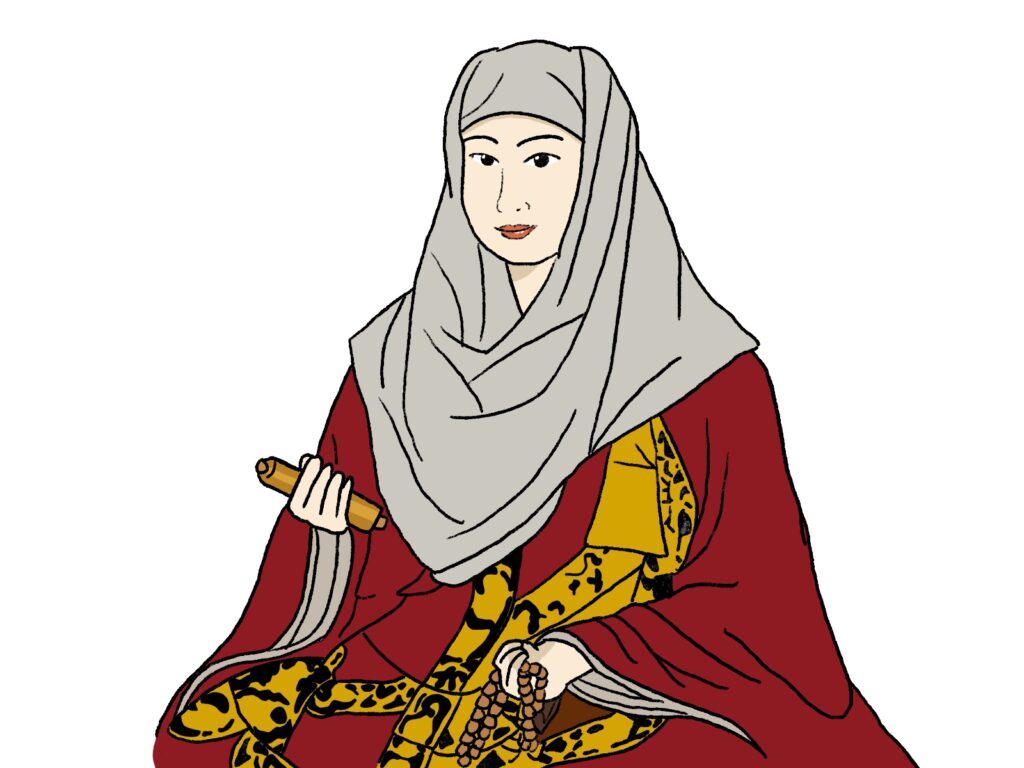

背景:後鳥羽上皇による院政の強化(朝廷の勢力挽回をはかる)
広大な皇室領荘園の集積
(b 西面の武士 )(上皇直轄郡)の設置
朝幕関係の不安定化
源氏将軍の断絶:3代将軍( c 源実朝 )を公卿が殺害(1219)
幕府からの皇族将軍招聘を後鳥羽上皇が拒否
藤原(九条)頼経を4代将軍に迎える(摂家将軍)
長江・倉橋両荘の地頭罷免を上皇が要求したが、幕府が拒否
経過:朝廷側:後鳥羽上皇の挙兵/北条義時の院宣(1221)
幕府軍側
東国御家人を結集
北条泰時(義時の子)・時房(義時の弟)軍を上京させて乱を鎮圧
泰時(義時の子)・時房(義時の弟)軍を上京させて乱を鎮圧
乱後の幕府の措置
仲恭天皇が廃位し、後堀河天皇が即位
3人の上皇配流
後鳥羽上皇は隠岐、( d 順徳 )上皇は佐渡、( e 土御門 )上皇は土佐
上皇方の武士・貴族の所領を没収(3,000余カ所)し、その地に地頭を任命
新補率法:給与保障の基準(得分の少ない場合に適用)
内容:田地1町につき1町の給田
反別5升の(f. 加徴米 )
山川からの収益の半分
新補率法が適用された地頭を新補地頭という
(g 六波羅探題 )を設置:朝廷の監視、京都の警備、尾張以西の御家人統括
長官に北条泰時(北方)・時房(南方)
乱の影響
幕府の影響力が畿内・西国に拡大
二元的支配の変化:幕府優位となり、皇位継承・朝廷の政治に干渉
